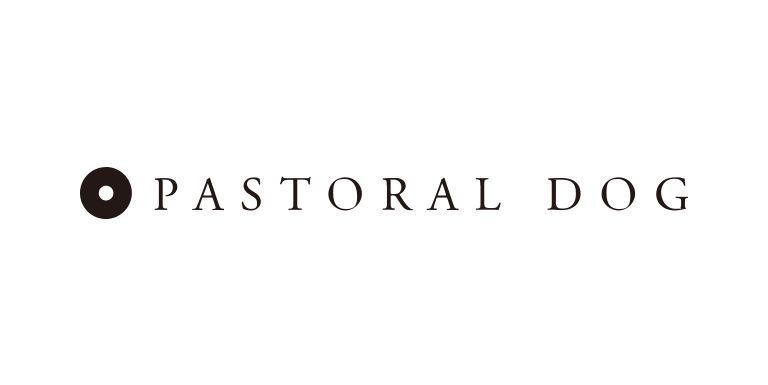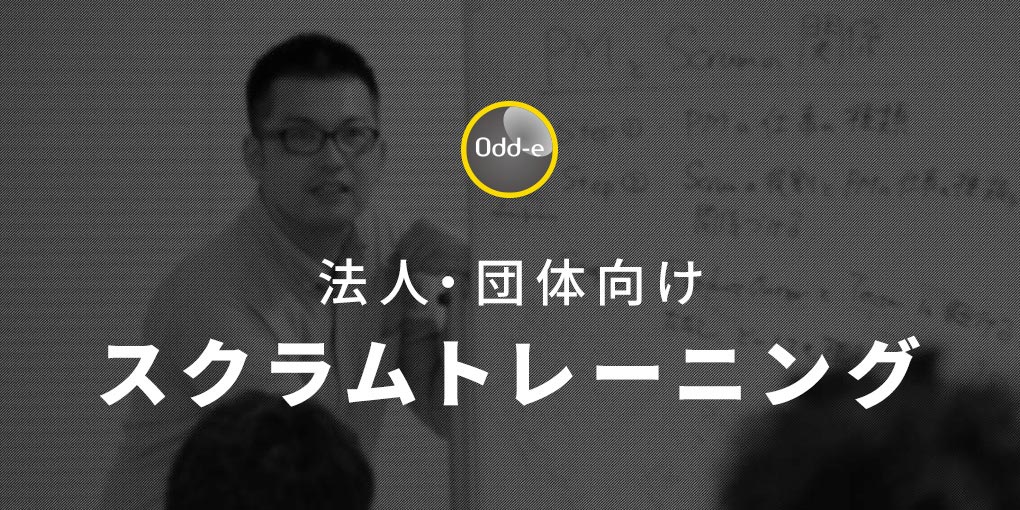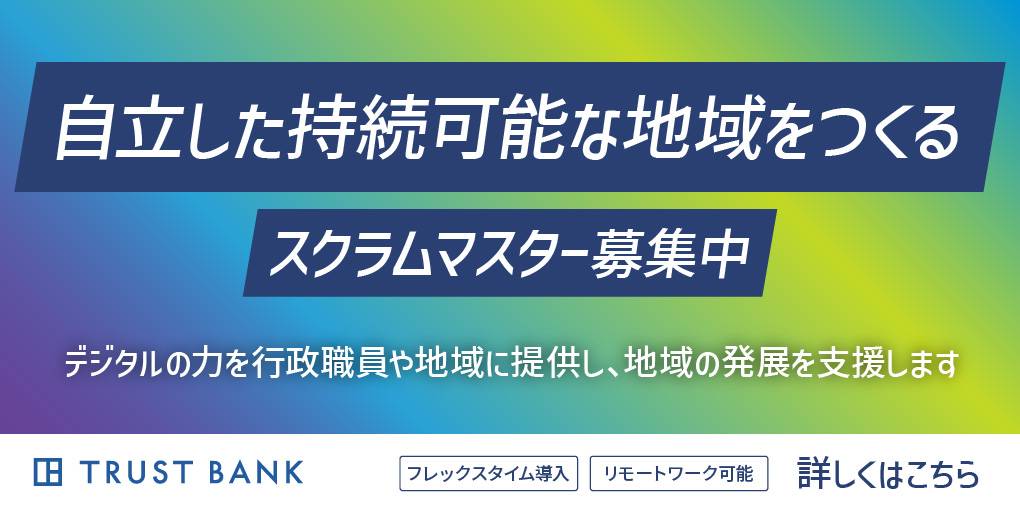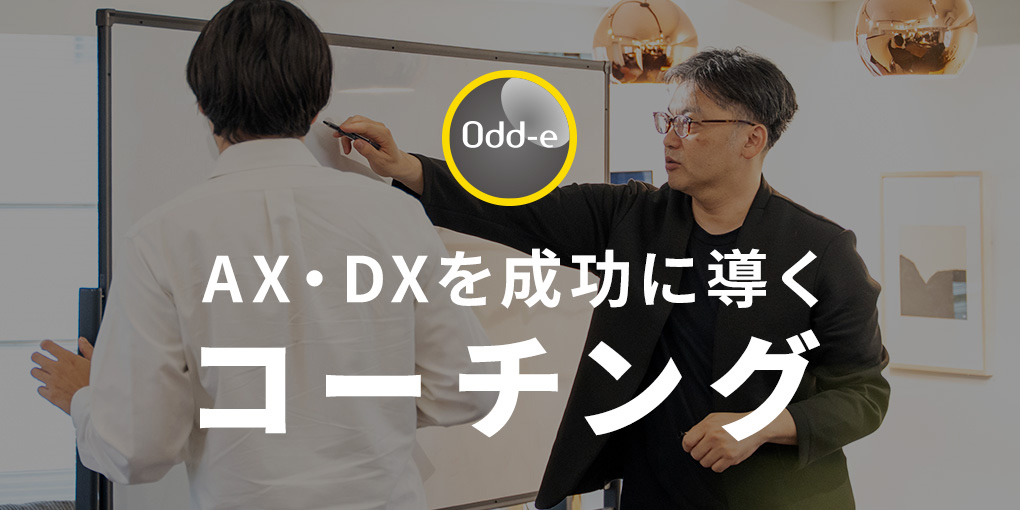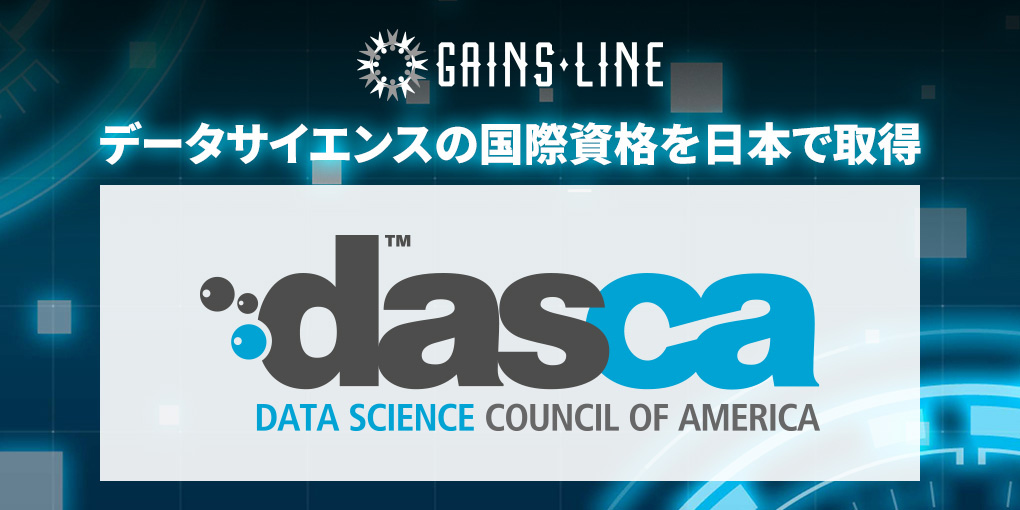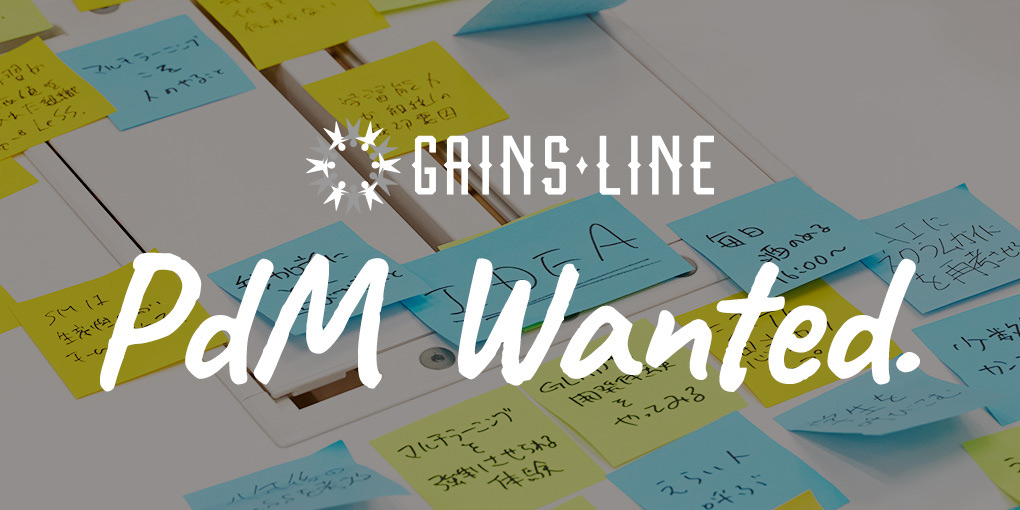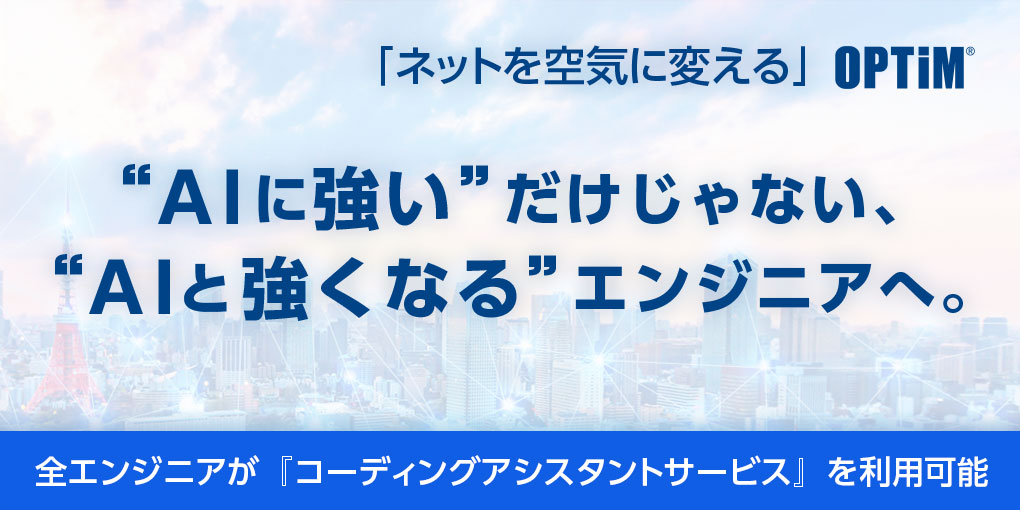About us
Global LeSS Conferenceは、大規模スクラム(Large-Scale Scrum: LeSS)を実践する世界中のプロフェッショナルが集う国際カンファレンスです。 単なる事例紹介にとどまらず、経験豊富な実践者やLeSSトレーナーとの深い対話を通じて、組織の変革とアジリティの本質を探求します。
LeSS’ Yoaké Asiaは、日本およびアジアにおけるLeSSの普及と実践を目的としたカンファレンスです。 2024年の第1回開催以来、アジア圏特有の組織課題や実践知を共有し、共に学び合う場として確かな足跡を刻んできました。
そして2026年10月、これら2つの潮流がひとつになります。 世界基準の知見とアジアの実践知が交差する共同開催イベント「2026 Global LeSS Conference Japan / LeSS’ Yoaké Asia 2026」を開催いたします。